太字をタップするとリンク先にジャンプできます
もとは100分de名著「善の研究」を見て、
「あーーーーー、oranjeにあるのってこれや!」
と思ったのがきっかけで、
そこで参考文献みたいなかたちで紹介されていたのが、
「無意識の構造」
でした。
「善の研究」は西田幾多郎ってひとが、
西洋から入ってきた「哲学」に、「日本オリジナルの哲学を」と
禅やらなんやかんやを解き明かして自論化したものです。
ま、ここでは、触れずに行きましょう。
(「純粋経験」がキーワードだと思いました)
「無意識の構造」は河合隼雄っていう、
京大名誉教授で、日本人として初めてユング研究所にてユング派分析家の資格を取得し、日本における分析心理学の普及実践に貢献した(wikipediaより)ひとが書いた本。
ユングは名前は聞いたこともあるかもしれませんが、
世界でもっとも有名な心理学者の一人。
ユング、アドラー、フロイトといえば、
「あ、聞いたことある」
という方もいらっしゃるのでは?
特にアドラーは数年前「嫌われる勇気」で有名になったりもしました。
アドラーとフロイトは同世代で、
ユングはフロイトの弟子、河合隼雄はまたその弟子ってことになるのでしょうか。
弟子って言っても、上下関係ないくらいみんなすごいひと。
アドラーは「自分は自分!今の自分は自分がつくりあげてきたんだ」という主張に対して、
ユングは「共同体の中の確かなひとりとして自分はいるんだ」という主張。
oranjeの雰囲気からすると一見アドラーっぽいんですが、
ユング系の河合隼雄の「無意識の構造」を読んでみると
「あーーーーー、oranjeにあるのってこれや!」
ってなりました。
本の中身は自己とか自我ってなーに?っていうのを無意識という視点で切り込んでます。
個人的におもしろいなーと思ったのは、
■「経験できなかった、あるいは今できていない像としての自分」=影
■起こったことをどうしても因果律にすがってしまうけどもそうではなく全体としてアレンジされてる
■一見無活動で身体的には退行していても、心的エネルギーとしては無意識に還っていっている
■ユングの無意識の構造は西洋的には理論的に詰め切ったところにあるが、東洋的(あるいは日本的に)は完成されたすがたとして人びとに浸透した発想として備わっている
あたりでしょうか。
僕らの支援の仕事もいろんな視点で話すことはできるんですが、
■そのひとの闇の部分を探す
■「めんどくさいなー」って思うときもあるよね
っていうのがスタンスの一つだったりもするので
その辺がパシーっとはまりました。
ま、一度読んでみてください◎
後半がまとまって書かれているので
そこだけでもいいかと思いますよー◎
Amazonはこちらをポチっと▼



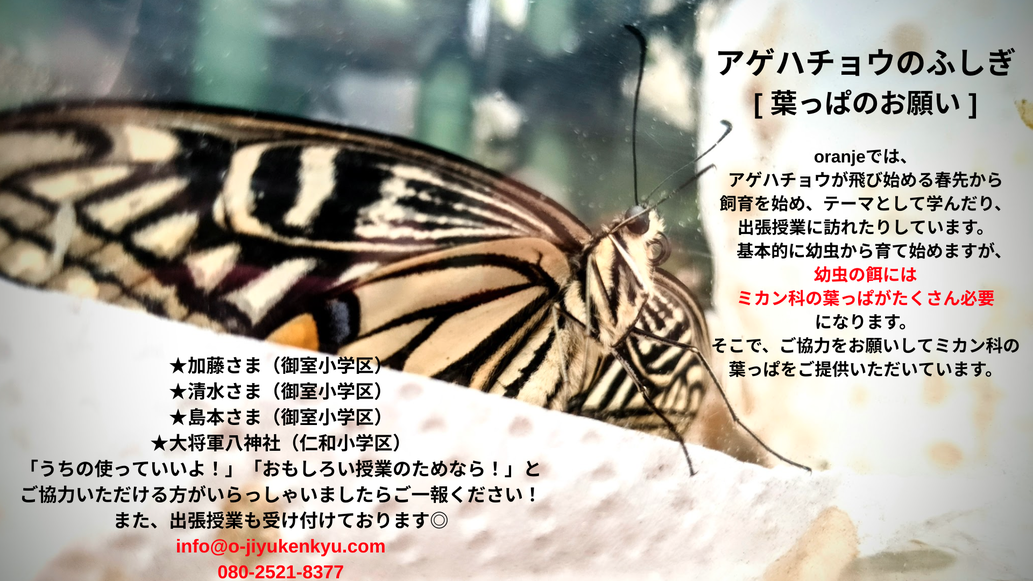



コメントをお書きください