第9回カバキャンプ、来てくれてありがとうございました! しおりにもある通り、鉄カバキャンプは日常性が強調され、自分たちで生活を作っていく、ということがほぼメインのプログラムのようなキャンプです。「???」となっていたひとも実感をもってすこしわかってくれたかな、と思っています。今回のキャンプでは「ほかの人とちがうことをする」ということをかなり口酸っぱく言いました。これがカバキャンプ(ベーシック)とは大きく違うところで、カバキャンプはどうしても「お手伝いする」という発想が強くなってしまいますが、手伝う、ということは誰かと同じことをいっしょにやる、ということなので、そこにあるやらなければいけないことを同時進行させるのが難しくなってしまいます。 過去の鉄カバの報告書を見返すと、「責任」、「自分でやる」、「自由」、「人権」について気づきを記録してきました。これまた鉄カバらしいな、と思います。ベーシックではどちらかというと、自分がどれだけ楽しんだかにスポットしますし、その中で自分がどれくらい「自分のことを自分でできるようになったか」を語ってもらいます。ところが、鉄カバは「自分のしたことで全体がどうなったか?」を自己評価しないといけません。だから上記のキーワードが出てきたのかなと思います。 改めてまとめておくと、鉄カバキャンプでは生活やプログラムを自分たちで作っていかないといけないので、「自分でできることを自分で知って(=メタ認知)」いないといけません。そして、「自分ができることをやりたいようにやる(=自由)」ことで、「全体をまあるく整理整頓(=責任)」できれば、それは「資本(自分のちからや、時間・お金など)をつかって目標を達成し、みんながハッピーになる(=人権意識)」ということになるように思います。 そして、ここにプラスαしたいのが、「倫理」です。例えば、いくらみんなゴミを持ちたくないからと言って、その辺に放りっぱなしにしてはいけないですよね?もちたくないものをもたなければハッピーかもしれませんが、それは倫理に反しています。倫理とは、社会生活をするうえで守るべき決まりごとや、善悪を判断する規準のことです。モラルなんて言い方をすることもありますね。 鉄カバでは「Leave No Trace(LNT)」という環境倫理のド入門資格を出しています。私たちは野外で生活している(させていただいている)ので、野外では野外の規準に従わないといけません。生活さえできればいい、プログラムが遂行できればいいのではないです。だから、「めんどくさっ」と思ったかもしれませんが、自分たちでこぼしてしまった米粒は一つ残らず拾ってもらいましたし、使ったことはないかもしれませんが汲み取り式のトイレで用足しをしてもらいました。それが今回のキャンプで守るべき規準だったからです。 そして、以上のことがすべてカチッとはまった瞬間が後半何回かありました。そのときの状態を「チームワークが良い」なんて言ったりするのかな、と思います。「自立のためにチャレンジし、気づきをもって日常へ帰る」のがカバキャンプですが、それを体現する鉄カバのチャレンジャーとして、すでに始まっているいまの日常からこの記事のことを実践してほしいなと思います。 2025.3.31 oranje代表・CABA camp統括 冨永岳(とみー)



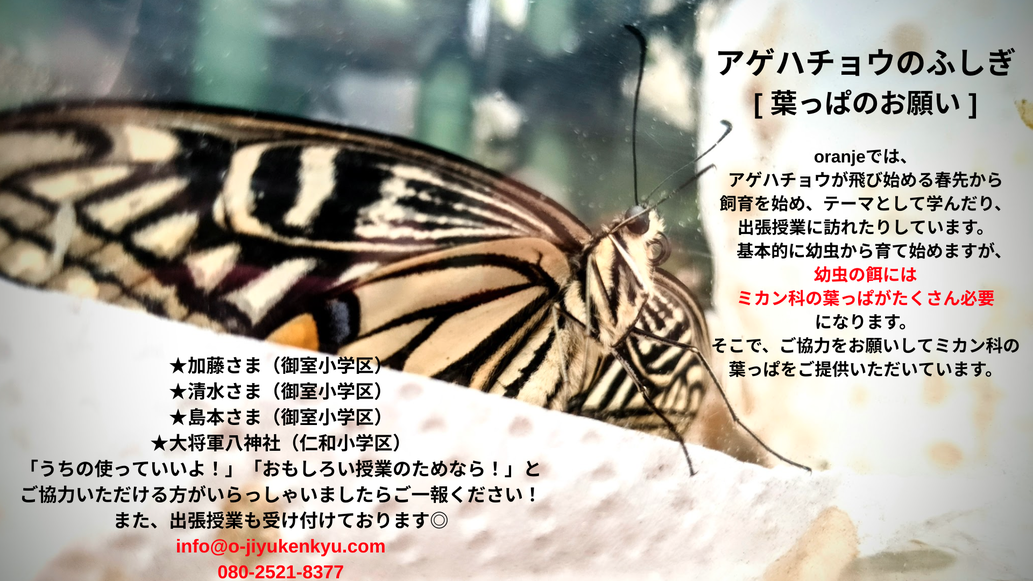



コメントをお書きください